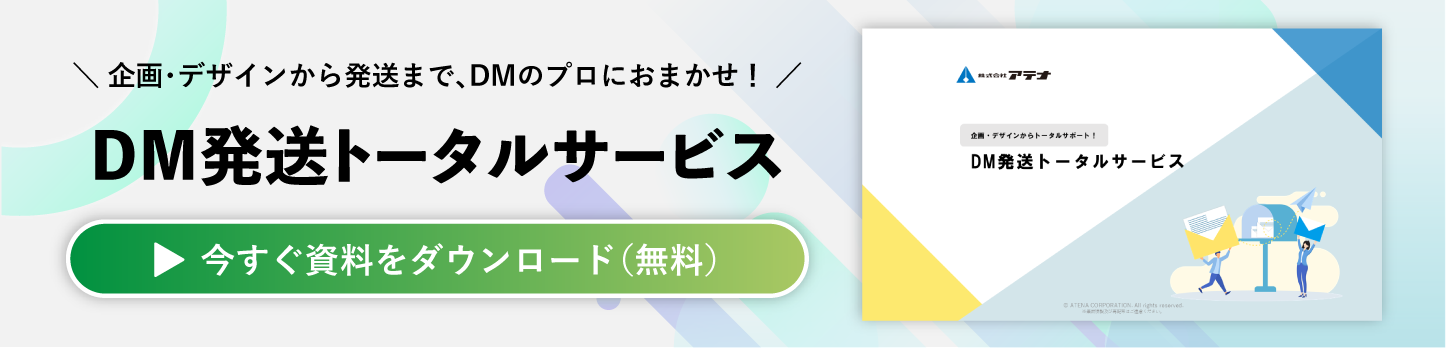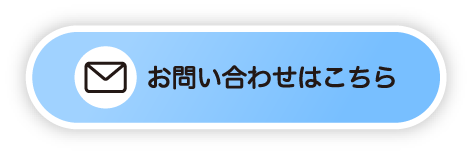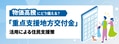デジタルアドレスとは何か?~7桁のコードが変える、住所と社会の未来~
先日、日本郵便は新たに「デジタルアドレス」を導入することを発表しました。「住所を書くのが面倒」「漢字の間違いが多い」「引っ越しのたびに変更が大変」などの日常の不便を解消する新しい仕組みです。
これは、従来の長い住所表記を7桁の英数字コードに置き換えるという、まさに住所のデジタル化を象徴する取り組みです。
本記事ではこのデジタルアドレスの仕組みと、私たちの暮らしにどのような変化をもたらすのかを詳しくご説明します。
目次[非表示]
- 1.デジタルアドレスとは?概要と仕組み
- 1.1.導入のステップと取得方法
- 2.現在の利用可能シーン
- 3.今後期待されるメリット
- 3.1.EC・物流業務における効率化
- 3.2.ユーザーの利便性向上
- 3.3.引っ越し時の手続き簡素化
- 3.4.社会インフラとしての可能性
- 4.法人向けAPIによる拡張性
- 4.1.普及に向けた課題
- 5.まとめ
デジタルアドレスとは?概要と仕組み
デジタルアドレスは、日本郵便の「ゆうID(※)」に登録された住所に対して発行されるランダムな7桁の英数字コードです。
※ゆうID:集配や再配達など日本郵政が提供するサービスを利用するための共通ID

この7桁のコードを入力するだけで、登録された住所情報が自動的に呼び出される仕組みになっています 。郵便番号と似ていますが、部屋番号まで含めた住所全てを表すことが出来る点が大きな違いです。
また、同じ住所に住む家族でもそれぞれが個別のデジタルアドレスを取得することが出来ます。これはデジタルアドレスが1人1つの「ゆうID」に紐づいて発行されるためです。したがって、原則として1人1人が異なるデジタルアドレスを持つことになります。
住所が変わっても、ゆうIDの登録住所を変更することでコードはそのまま使い続けられます。
なお、住所や名前から、他人のデジタルアドレスを調べることはできません。
導入のステップと取得方法
郵便局アプリまたはWEBブラウザから以下のステップで取得が可能です。どちらも事前にゆうIDを登録する必要がありますが、無料で取得・利用が可能です。
※窓口での取得は出来ないため、注意が必要です
【アプリ版】
① ゆうID登録
② 郵便局アプリにゆうIDでログイン
③ デジタルアドレス取得
【Web版】
① ゆうID登録
② デジタルアドレスWEB版にゆうIDでログイン
③ デジタルアドレス取得
現在の利用可能シーン
現在、デジタルアドレスは郵便局アプリにおける「送り状作成」機能で利用することが可能です。
住所を1から入力する手間が省けるため便利ですが、現時点ではデジタルアドレスだけで郵便物や荷物を送ることは出来ません。デジタルアドレスはあくまでもWEBサービスで郵送を行う際の入力補助の役割として使われています。

今は郵便サービスのみでの利用に限られていますが、今後は日本郵便をはじめ、そのパートナー企業によりデジタルアドレスが利用出来るサービスを順次拡大するとしています。
今後期待されるメリット
デジタルアドレスは、単なる住所表記の短縮に留まらず、業務効率化やユーザー体験の向上、さらには社会インフラとしての可能性まで、多岐にわたるメリットが期待されています。
EC・物流業務における効率化
ECサイトやオンラインショップで買い物をする際に利用出来るようになれば、住所入力の手間や誤入力のリスクが大幅に削減されます。贈り物をする際にも正確な住所情報の共有が可能となり、再配達や誤配達のリスクを低減させることが出来ます。これにより、物流業務全体の効率化にも寄与するでしょう。
ユーザーの利便性向上
郵便サービスに留まらず、例えば、病院の問診票や行政の申請書類、会員登録の記入用紙など、日常生活の中で広く利用可能になれば、住所を手書きする際の手間が大幅に軽減されます。
また、外国人や高齢者の方にとっても、複雑な日本の住所を覚える必要が無くなり、サービスへのアクセス性が向上します。
引っ越し時の手続き簡素化
従来は引っ越しの度に、登録している各種サービスや機関に対して住所変更手続きを行う必要がありましたが、デジタルアドレスを利用すれば、ゆうID上の住所情報を変更するだけでコードは変わらないため、住所変更の手間が大幅に軽減されます。
社会インフラとしての可能性
デジタルアドレスは以下のような分野でも活用が期待されています。
- 災害時の避難所情報の即時共有
- タクシー配車や無人配送の精度向上
- 地図アプリやSNSとの連携による位置情報の共有
行政・医療・災害対応・物流・観光・教育など、あらゆる分野での情報共有と連携の基盤となる可能性を秘めており、社会全体のデジタル化を左右する重要な鍵となるでしょう。
法人向けAPIによる拡張性
日本郵便は今後のサービス拡大に向けて、法人向けの「郵便番号・デジタルアドレスAPI」の提供も開始しました。 これにより、企業はデジタルアドレスから正確な住所を取得出来るようになり、デジタルアドレスをキーとしたデータの統合や住所の最新化などが可能になります。
※法人向け:郵便番号・デジタルアドレス for Biz | 日本郵便株式会社
例えばECサイトを運営する企業であれば、API連携により発送前に最新の住所情報を呼び出し、補正を行うことが出来るため、スムーズな配送を実現することが出来るでしょう。
企業はこのサービスを活用することでデジタルアドレスに対応したシステムやインフラの整備を進めていくことが求められます。
様々な事業者がこのサービスを導入することで、病院、行政手続き、教育現場など、幅広い分野へのデジタルアドレスの普及が期待されています。
普及に向けた課題
しかし、各種サービスにおけるAPI連携やシステム対応には一定のハードルがあるため、実際の普及にはまだまだ時間がかかることが予想されます。 また、APIキーの管理や不正アクセス対策など、運用やセキュリティに関する整備も求められるでしょう。事業者としても1ユーザーとしても、今後の動向を注視していくことが重要です。
まとめ
デジタルアドレスは、私たちの「住所の概念」を根本から変える可能性を持つ革新的な仕組みです。その導入は、単なる利便性の向上にとどまらず、社会全体のデジタル化と効率化を加速させる鍵となるでしょう。
今後、どれだけ多くの企業や自治体がこの仕組みを取り入れ、どのように活用していくかが、デジタルアドレスの真価を決めることになります。これまで当たり前だった「住所を書く」という日常の行為が、近い将来、まったく新しい形に変わるかもしれません。
このように私たちの身近なもののデジタル化が進んでいきますが、取り組み内容によっては自社だけで対応することが難しい場合もあるかもしれません。
株式会社アテナではデジタルツールを活用した業務のデジタル化・効率化をサポートするソリューションをご提供しています。
BPO業務で培ったノウハウと、デジタルツールの組み合わせで貴社のDX推進を全面的にサポートしますので、気になった方は是非ご相談ください。