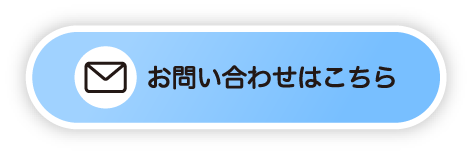<アテナの生成AI導入ストーリー②>
生成AIの社内定着へ──アテナ流導入ステップと現場の課題
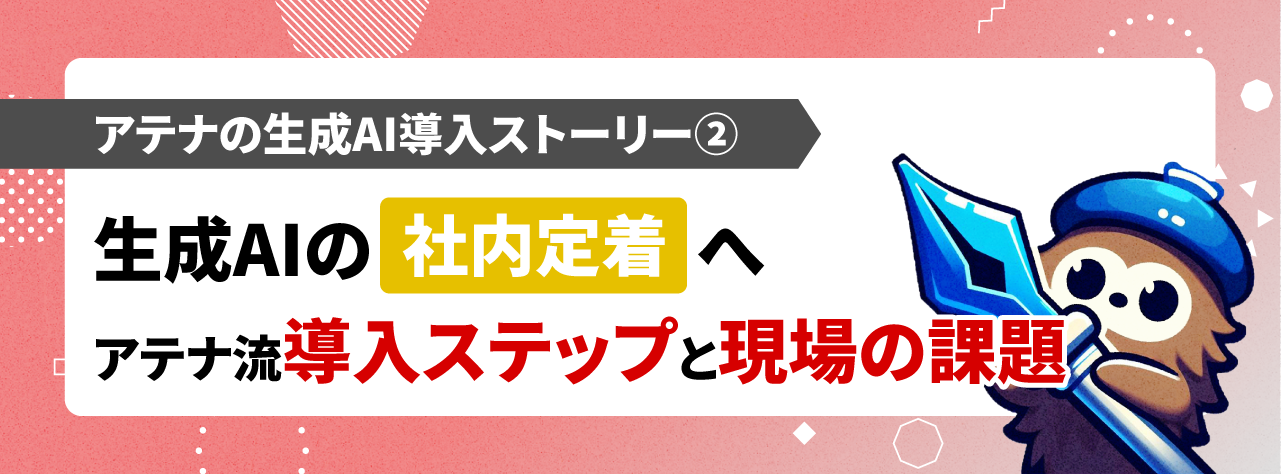
前回の記事では、アテナが生成AIをどのように導入し、社内での基盤を整えていったか、その舞台裏や工夫についてご紹介しました。
今回はさらに一歩踏み込み、実際に現場でどのように生成AIが根付いていったのか、具体的な活用事例や導入プロセス、全社的な定着の過程で直面した課題、そして今後の展望について詳しくお伝えします。
※関連コラムはこちら
段階的な導入プロセス

生成AIの導入のきっかけとなった最初の成功体験から約1年をかけて段階的に全社展開まで導入を進めていきました。
STEP | 01 |
初期段階(導入1~4ヶ月):基盤作りと課題発見
まず、各部門から数名ずつ選抜した約20名のトライアルメンバーから開始しました。
この初期メンバーは、新しい技術への関心が高く、積極的に試行錯誤を繰り返す意欲を持った人材を選びました。彼らがどのようにこの技術を活用し、どの部分に不便さを感じるのかを詳細に観察し、分析することから始めたのです。
トライアルメンバーからは、「プロンプトの書き方がわからない」、「期待した回答が得られない」、「使うタイミングが分からない」といった率直なフィードバックが寄せられました。これを受けて、基本的な使い方ガイドやよく使われるプロンプト例、具体的な活用シーンの一覧などを整備し、誰もが迷わず使うことが出来る環境づくりを進めました。
さらにこの段階で、セキュリティガイドラインの策定も並行して実施しました。「個人情報は入力しない」、「出力結果は必ず人間が確認する」といった基本ルールを定め、安全性を確保する基盤を整えています。
STEP | 02 |
拡大段階(導入5~8ヶ月):成功事例の蓄積と横展開
トライアルメンバーから具体的な成功事例が出始めると、その効果を他部門にも紹介し始めました。当初はTeams上で活用事例や使い方を定期的に発信していましたが、大きな反応は得られませんでした。
そこで、単に使い方を「教える」のではなく、「実際に使っている場面を見せる」アプローチに切り替えました。例えば、プロジェクトの議事録をAIで作成し、それをそのまま成果物として共有したり、あるいは、業務上の困りごとにAIを組み込んだサポートシステムを提供して、自然に「AIがある業務体験」を体験してもらうといった方法です。
この段階では利用者は50名ほどに拡大し、技術系以外の部門でも活用事例が生まれていきました。営業部門での文書チェックや総務部門での通知文作成など、多様な使い方が自然に広がっていきました。
STEP | 03 |
定着段階(導入9~12ヶ月):全社展開と文化の変化
段階的な拡大を経て、最終的に全社員へのアクセス権を開放しました。この頃になると、社内での反応も大きく変わってきていました。
導入当初は「生成AIってなに?」「難しそう」という反応が多かったのですが、最近では会議中に「わからなかったのでアテモン(※)に聞いてみました」や「アテモンがこんな提案をしてくれました」といった発言が自然に交わされるようになっています。
特に印象的だったのは、これまでITツールにあまり積極的でなかった社員が、「アテモンに相談してみよう」と気軽に声をかける姿を見た時でした。システムやツールとしてではなく、相談相手として認識されている証拠だと感じています。

(※)アテナの公式AIキャラクター「アテモン」
アテナのロゴをモチーフにした“万年筆”を手にする猿で、名称は社内公募により「アテナ+モンキー」から生まれました。
落ち着いていて冷静な性格ですが、感謝されると喜ぶ一面も。
文章処理が得意で、数学や流行は少し苦手です。
※関連コラムはこちら
セキュリティとガバナンスへの配慮
生成AIの導入にあたっては、「生成AIガイドライン」を制定しました。最も重視しているのは、個人情報保護・著作権の確保・生成結果の信頼性です。
具体的には、
- 個人情報を生成AIに入力しない
- 第三者の著作物や機密情報を無断で入力しない
- 生成結果は正確とは限らないため、必ず人間が確認する
- 生成物を利用する際は、著作権や利用規約に反しないことを確認する
といったルールを明記し、利用者には必ず遵守してもらっています。
あわせて、AIが出力した結果に誤りや問題があった場合でも、最終的な判断と責任は利用者にあることを周知しています。
現在の活用状況
2025年8月時点、全社員の約7割が月1回以上生成AIを利用するまでになり、利用頻度も安定してきました。各部門では以下のような活用が進んでいます。
- 営業部門
生成AIを活用して文書チェックを行うことで、不適切な表現を自動で検出出来るようになりました。この取り組みにより、年間で約96時間の業務時間を削減することに成功しています。この結果、営業担当者はチェック作業に使っていた時間を、商談準備や顧客対応といった本来の業務に充てられるようになっています。
- 開発部門
仕様書の整理やコードレビューの補助に加え、エラー原因の分析にも活用しています。その結果、これまで一日がかりだった修正作業が、わずか1時間程度で完了するケースも出ています。
- 現業部門
日報の要約や作業手順書の作成支援など、現場業務の効率化に貢献しています。ただし、これらの効果測定はまだ一部に限られており、全社的な定量評価は至っていません。今後は各部門での成果を集計・分析し、より正確な把握するとともに、活用ノウハウを全社に共有していく予定です。
具体的な活用事例については、今後のコラムで詳しくご紹介していきます。
直面している現実的な課題

生成AIの活用が広がってきた一方で、依然として大きな課題が残っています。それは「知識や経験の不足による活用格差」です。うまく使いこなせない、何を聞けば良いかわからない、活用出来る場面が思い浮かばない。こうした状態では、AIを業務に取り入れる機会そのものが減り、経験値の蓄積も進みません。その結果、利用者と未利用者の差が広がるという負の循環が生じます。
背景には、操作スキルだけでなく「問いの立て方」「情報の取捨選択」「結果を踏まえて次のアクションを決める」といったソフトスキルの差も重要です。生成AIは与えられた指示に従って結果を出力するため、質問が曖昧であると結果も不十分になる可能性があります。逆に、目的や条件を的確に伝えると、短時間で高品質な成果を引き出すことができます。
このように、AI活用の成功には技術力だけでなく、こうした人間側の能力育成が不可欠だとされています。
また、すべての業務において、期待通りの成果が得られているわけではありません。特に、Q&A業務では、AIが回答を提示しても、その正確性を裏付けるエビデンスが必要となり、処理時間の短縮効果は限定的でした。これは、AIの強みが「一次案の生成」であり、「最終判断や検証」は依然として人間が担うべき領域であることを示しています。
今後の展望
今後は、先程ご説明した生成AIの特性を前提に業務適合性を見極め、AIが効果を発揮しやすい領域に集中投資すること、そして研修や事例共有を通じてソフトスキルの底上げを図ること、この両輪で全社的な活用レベルの向上を目指していきたいと考えています。
また、全社的に活用は進んでいるものの、効果測定はまだ一部にとどまり、全社的な定量評価は十分に進んでいません。そのため、今後は各部門での成果を集計・分析することで、より正確な効果を把握するとともに、その活用ノウハウを全社で共有していく予定です。
生成AI導入を振り返って
振り返ると、生成AIは全社を一変させる即効薬ではありませんでした。しかし、日常業務において「相談相手」や「表現を整える補助役」としての役割を着実に広げています。完璧な答えを求めるのではなく、思考のきっかけや作業の効率化に繋げる存在として、社内文化に徐々に根づき始めています。
BPO・DM発送事業という本業において、顧客サービスの品質向上が最優先であることに変わりはありません。生成AIは、その品質向上を支える有効な道具の一つとして、今後も現場の声を生かしながら成長させていきます。
20人のメンバーから始まった取り組みは、社員の約7割が日常的に利用するまでに広がり、具体的な業務時間削減も実現しました。
変化の激しい時代において、新しい技術を恐れずに取り入れ、現場の声を聞きながら育てていく姿勢こそが、私たちの強みだと考えています。生成AIとの歩みはまだ始まったばかりですが、この経験を通じて得た知見を、今後のサービス向上に繋げていきたいと思います。
- 関連ソリューション